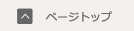© Hanya Chlala/Arena PAL
コンポージアム2013では、現代イギリス作曲界の巨匠ハリソン・バートウィスルの世界を特集します。バートウィスルに学んだ作曲家、なかにしあかね氏に、巨匠の独創性、素顔のエピソードをご寄稿いただきました。
サー・ハリーの音楽

サー・ハリソン・バートウィスルの音楽を一言で表すのは難しい。ひとたびオーケストラが鳴れば、大地が鼓動し、時は勝利し、深閑とした夜の闇が広がり、楽器が群れをなして大気を震わせる。室内楽作品の多くに見られる舞台上の儀式は、室内楽の概念を軽々と飛び越え、音に新たな意味を生み出す。『ガウェイン』『セカンド・ミセス・コング』『ミノタウルス』などのオペラ作品に見られる壮大な集中力の持続と衝撃の連続、《シルヴァリー・エアー》の繊細な透明感、《マスク・オブ・オルフェウス》の緻密で複雑な何層もの構造。《パルス・シャドウズ》は長年かかって書き溜めたツェランの詩による9つの歌が、9つの弦楽四重奏曲の組み合わせで再構築されることにより、立体的なドラマ性を付与されている。
「ドラマ性」は重要なキーワードのひとつである。声を含む作品も多いが、そうでない器楽作品やオーケストラ作品においても、空間における劇場性、発想における劇性、楽器群の対話、楽曲構築におけるドラマ・・・広く深い意味で、可視的あるいは潜在的に、そこには必ずドラマがある。
彼のアイデアは常に新しく、何ものにも似ていない。彼のアイデアは、アイデアに終わらない。彼の音楽は常に、物語の本質、音の本質を強く希求し、結実する。ひとたび彼の音楽にとらえられると、ただ息を呑み、胸ぐらをつかまれ、宇宙の彼方から地の果てまで運ばれるしかない。彼の音楽は生命の力と輝きに満ち、そこには神聖なまでの儀式性と、原始の根源的なエネルギーが共存する。
セレブリティ・ハリー
サー・ハリソン・バートウィスルの「サー」の称号は、ナイトに叙任された男性の肩書で、サー・ハリーは1988年に叙勲されている。その後2001年にはCompanion of Honour(名誉勲爵士)にも叙され、押しも押されもせぬセレブリティである。「最も偉大な作曲家」という大見出しと共に、『ガーディアン』紙の一面にサー・ハリーの顔が全面アップになり、彼のウィルトシャーの自宅「シルクハウス」の庭は造成された当時、ガーデニング雑誌で特集を組まれていた。今世紀に入っては発言の重みをさらに増された模様で、どこで何を言ったといちいち騒がれ、ヨーロッパの名だたる音楽祭で特集が組まれている。

私がロンドン大学キングスカレッジの博士課程でバートウィスル門下であったのは1995年から1999年までで、彼は1995年から2001年まで、ヘンリー・パーセル・プロフェッサーという冠つきの教授であった。バートウィスルがキングスで教える、というニュースは当時相当なセンセーションを巻き起こし、ヨーロッパ、アジア、南北アメリカ大陸からも入学希望者が殺到した。レッスンはもっぱら当時彼がテムズ河畔に持っていたマンションに伺うか、ロンドンから3時間車を飛ばしてシルクハウスへ泊りがけで伺うかだったが、ある日「ちょうどロンドンでダニーとリハーサルしているからBBCのスタジオに来い」と言われて行ってみると、「ダニー」はダニエル・バレンボイムで、私は自分の譜面などろくに見て頂けなかった代わりに、BBCシンフォニーの新曲リハーサルをまるまる聴くという生きた勉強をさせて頂いたのだった。
サー・ハリーは生まれつきのセレブなのではなく、自身の音楽のみでその地位を築いた。名誉は後からついてきた。その音楽があまりにも圧倒的であるがゆえに、彼は崇拝される。
農場の少年ハリー

イングランド北西部のアクリントンの農場の少年であった頃そのままの純粋な好奇心を、サー・ハリーは今も大切に持ち続けているように見える。しかしサー・ハリーともなると事はなかなかそう簡単ではない。前回2000年の来日時に京都旅行にお連れした時には、夜、街を歩きたいと言われるのでご案内しようとしたら、「おまえは帰れ。」「まさか!迷いますよ!アンドリュー(マネージャー)に叱られます。」「アンドリューは忘れろ。俺は迷いたいんだ!」・・・招かれる国、行く先々で、付き人となる方々のご苦労を思う。京都では、竜安寺の石庭も、大好きな黒澤明監督の定宿であった町屋の宿も、楽しんで下さったのではあるが、最もお気に入りの場所となったのは、どうやらJR京都駅の大階段だった。「造られた当初は京都の景観に合わないという意見もあったんですよ」「なぜだ!素晴らしいじゃないか!」私と奥様のシーラをショッピングへと追い払って、ご自分は大階段に座って下から眺めたり、上から見下ろしたり、飽きずに過ごされたのだった。そう言えばロンドンのテート・モダン(近現代美術館)の開館式典に音楽を委嘱された時も、発電所を改造した巨大な空間にどう楽器を配置しどう使うか、それがどれほどエキサイティングかを、熱心に説明して下さった。建造物における「Grand」は、彼の心をくすぐる鍵のひとつであるらしい。
御年78歳の恩師に対して「少年のような」は、最大級の敬意を持った賛辞である。「ぐにゃぐにゃ曲げられる眼鏡」なるものを入手して「見ろ!曲げられる眼鏡だぞ!」と自慢した次の瞬間にポキッと折ってしまう。ベルリンに招かれて用意された五つ星ホテルでとっくにくつろいでいるはずの時間に、なぜかスーツケースを引きずりながら雨の夜のベルリンの街を彷徨う・・・失敗を恐れてはならぬと、身をもって教えて下さるのである。
指導者サー・ハリー
「ハリーはどのように教えるのか?」という質問を、何度受けたかわからない。「生徒によって、その生徒の段階によって、違うと思う」と答えてきた。その、あくまでもほんの一例に過ぎないある日のサー・ハリーと私を描写するとこうなる。
沈黙。
「どうだ?」
沈黙。
「考えてます(I'm thinking.)」
「いや、おまえは沈んでいる(No, you are sinking.)」。
毎回、禅問答のような会話の中に、名言と冗談が半々くらいの割合で織り込まれた。譜面に手を加えるようなことは、一切された記憶がない。しばらく私の譜面を眺めた後、「こういうことを考えたことがあるか」「この詩集を読め」「テート・ギャラリーへ行ってロスコを見て来い」「知ってるか。エスキモーは雪を描写するのに100以上の言葉を持っている」・・・彼は私に曲の作り方は教えなかった。ただ、「私にとって」曲を作るとはどういうことか、考え抜くとはどういうことかを、繰り返し考えさせた。「記譜法」ではなく、音を本当に楽譜に移すとはどういうことかを、「楽器法」や「管弦楽法」ではなく、本当に楽器を扱うとはどういうことかを、私自身のやり方として確立させようとした。私が何を書くかではなく、どう書くかを確立するまでが、自分の仕事だと思っておられたようだった。音楽のスタイルに関わらず、表現として真に練り上げられたもの、創造性豊かな文化、人の営みとして興味深い現象を、彼は尊重する。同門のうち博士号取得までたどり着いた数人の作風は見事なまでにばらばらであり、今は世界の各地に散らばって、それぞれに、確信を持って自由気儘にやっている。このことが、何よりもサー・ハリーの指導者としての偉大さを物語っている。
以上3000字を費やしても、彼の、汲めども尽きぬ魅力を伝えられた気がしない。それが、サー・ハリーである。ぜひ、彼の音楽を聴き、コンポージアムで来日する彼の肉声に触れ、あなた自身の五感で、この、同時代に生きる巨人の存在を感じて欲しい。
東京オペラシティArts友の会会報誌「tree」Vol.97(2013年4月号)より


![[特別寄稿] サー・ハリソン・バートウィスルという巨人](/concert/compo/2013/common/img/banner_essay_under.jpg)