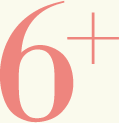第三部
日本における受容
ゲスト:平山景子(ファッション・ディレクター)、栗野宏文(ユナイテッドアローズ上級顧問)
コーディネーター:西谷真理子(『ハイファッション』副編集長)
 西谷:では第三部を始めたいと思います。まずゲストのお二人をご紹介します。こちらが、『花椿』編集長を長年務め、今はフリーのファッション・ディレクターをやっていらっしゃる平山景子さん、そちらはユナイテッドアローズの上級顧問の栗野さんです。お二人ともたぶん皆さんご存じだと思います。平山さんは、70年代からパリコレクションをご覧になっていて、70年代に資生堂の主催でパリのデザイナーを呼んだイベントを企画なさったり、80年代のパリコレクションも見て来ていらっしゃる。その後、マルタン・マルジェラやアントワープ・シックスの、ちょうどデビューの頃もご覧になってらっしゃるというので、彼らがどういった形でそれまでのファッションと違う要素を持ち込んだのかを、生の言葉で話して頂きたいと思いました。それと平山さんは、デザイナーを見る視点がトレンドとかビジネスとかではなく、クリエーションをきちんとつかんで、デザイナーにインタビューもやって来てらっしゃいます。
一方栗野さんは、もともとビームスにいらして、そこからユナイテッドアローズを立ち上げたスタッフの一人で、バイヤーの立場からコレクションを見ていらしたのですが、私の雑誌『ハイファッション』でも、よく原稿をお願いしています。単なるバイヤーを超えた、ジャーナリスティックな面も持っていらっしゃる方で、ことアントワープに関しては、とても重要な仕掛け人で、アントワープファッションを、日本の中に定着させたと同時に、それを文化にした方だと思っております。
最初にまず平山さんから。ロンドンの展示会もご覧になったそうですが、一体どんな感じだったのでしょう、パリコレクションで、ティエリー・ミュグレーだとかモンタナとかケンゾーとかゴルチエとか、そういう人たちが一つのムードをつくっているところに、どんな感じで彼らのファッションが登場したのか、個人的な感想も含めて話して頂けますか。
西谷:では第三部を始めたいと思います。まずゲストのお二人をご紹介します。こちらが、『花椿』編集長を長年務め、今はフリーのファッション・ディレクターをやっていらっしゃる平山景子さん、そちらはユナイテッドアローズの上級顧問の栗野さんです。お二人ともたぶん皆さんご存じだと思います。平山さんは、70年代からパリコレクションをご覧になっていて、70年代に資生堂の主催でパリのデザイナーを呼んだイベントを企画なさったり、80年代のパリコレクションも見て来ていらっしゃる。その後、マルタン・マルジェラやアントワープ・シックスの、ちょうどデビューの頃もご覧になってらっしゃるというので、彼らがどういった形でそれまでのファッションと違う要素を持ち込んだのかを、生の言葉で話して頂きたいと思いました。それと平山さんは、デザイナーを見る視点がトレンドとかビジネスとかではなく、クリエーションをきちんとつかんで、デザイナーにインタビューもやって来てらっしゃいます。
一方栗野さんは、もともとビームスにいらして、そこからユナイテッドアローズを立ち上げたスタッフの一人で、バイヤーの立場からコレクションを見ていらしたのですが、私の雑誌『ハイファッション』でも、よく原稿をお願いしています。単なるバイヤーを超えた、ジャーナリスティックな面も持っていらっしゃる方で、ことアントワープに関しては、とても重要な仕掛け人で、アントワープファッションを、日本の中に定着させたと同時に、それを文化にした方だと思っております。
最初にまず平山さんから。ロンドンの展示会もご覧になったそうですが、一体どんな感じだったのでしょう、パリコレクションで、ティエリー・ミュグレーだとかモンタナとかケンゾーとかゴルチエとか、そういう人たちが一つのムードをつくっているところに、どんな感じで彼らのファッションが登場したのか、個人的な感想も含めて話して頂けますか。
平山景子
80年代に黒い旋風で川久保玲さんと山本耀司さんが頑張って出てきたわけです。それは非常に衝撃的なことだったわけですね、特にパリのファッション界においては。で、その時に、もちろんミュグレーとか、アライア、モンタナという人たちもいたのですけれども、この新しい異分子が入って来たことは、パリコレの活性化として有効だったわけです。80年代はコムデギャルソン、ヨウジヤマモト、そしてゴルチエ、ミュグレー。じゃあ90年代は誰だろうという、その話は既に80年代の終わりぐらいに始まっていたわけなのですね。私と大変親しい、パリの大御所だったメルカ・トレアントンさんという人が、この次はたぶん北欧か北の方の人が出て来るのじゃないかっていうようなこと、つまり今まで出て来てない人たちが必ず来るだろうという予測をするわけですよね。だから21世紀は、まだアフリカの人は出て来ていないから、それじゃっていうこともあるかもしれません。
89年にマルタン・マルジェラがデビューするのですが、マルジェラは「6人」とはちょっと違っていて、とにかくジャン=ポール・ゴルチエのフリークだったらしいのです。ゴルチエのアシスタントになりたいということで、卒業後すぐパリに行ってしまったんです。それで、アシスタントになった。ジャン=ポール・ゴルチエに、「彼はどうやってアシスタントになったのですか」、と聞いたところ、「いつの間にかいたんですよ」と言っていましたが、パリのファッション界の人たちも、ゴルチエでメンズの服を任されていたマルジェラのことはある程度わかっていたのすね。そしてマルジェラ自身もたぶんゴルチエのところにいる間に、今のファッション界のシステムとか、そういうものが本当に良いのだろうかという疑問符を持ち始めたと思うのです。そして実際に自分がやる時には、こういう風にやりたいということを、非常に深く考えていたのじゃないかと思います。89年第一回目の彼のショーは、これも伝説的なのですが、招待状が電報だったんです。で、私は本当に馬鹿で、これは一体何だって捨ててしまったのです。その電報が、まさか招待状だとは思わずに。もっとおかしな招待状はいっぱい届いていたのに、電報?、これは何かの間違いだろうと思って。それで行けなかったのです、第一回目は。その後、もうショーの会場自体が衝撃的でした。野原でやったり、使われていない地下鉄の駅の構内でやったりとか。どこに何があるかわからないでショー会場へ出掛けていくという体験は初めてでした。そういうふうに、非常に用心深く、自分の考えていることを、完璧にやり遂げていくという、マルジェラの姿勢が、いろいろなことを覆していったと私は思うんですね。今この形でパリコレクションが存在していくとしたら、マルジェラのことを抜きには語れないと思います。彼が押し進めて行ったこと、それはアントワープの学校とか、国民性とか、それも含めて考えて行かなければなりませんが。
西谷:第一回目は見逃したとおっしゃいましたが、マルジェラのコレクションを初めてご覧になって、その洋服自体にはどんな感想をお持ちになりましたか?
平山:洋服もこれまでに見たことがない服でした。私の世代は、コムデギャルソンという存在があって、そこで一度破壊の経験をしているわけですね、服の。でもマルジェラは破壊の仕方が違う発想で行われているわけです。最初はお金がなかったので、ほとんどが、古着を解体して作った服です。だから一見汚く見えるのですけど、ジャケットをカットして縫い直したり、自分の形に持っていくという、その形そのものに大変驚きました。それで、もちろんすぐに展示会に行きました。着られない服もたくさんあるけれども、私たちはまだ服を面白く着られるのだなという、好奇心を持ちました。
西谷:栗野さんの場合もアントワープは、最初はマルジェラからなのでしょうか?

栗野宏文
1993年にアントワープ・アカデミーの30周年の記念のインスタレーションがあって、それは面白そうだから絶対行こうと思って、ちょうど9月末で終わってしまうのですが、ぎりぎりの最後の数日間に行けたのですね。行った時にリンダ・ロッパさんとそれからリンダさんのご主人のディルクさんとカレル・フォンテインと、それからドリース・ヴァン・ノーテンの営業の一番偉い人だったクリスティーヌ・マテイスという女性がいらして、その人たちに案内してもらったのです。で、初めてアントワープに行った時に、アカデミーの回顧展を案内してくれたのがリンダ・ロッパさんだったというのが、自分にとっても最高にラッキーだったわけですね。シュルレアリスム展をダリに案内してもらうようなものですよね。全部知っている人に案内してもらったみたいな、その時に、これはただごとじゃないなと思って、重松さんがモノとして導入してくれたアントワープのデザイナーのものを、僕は僕なりにちゃんと引き継いでいかなきゃいけないなと思いました。そのインスタレーションの中に、リーヴ・ヴァン・ホルプとウィム・ニールスの展示があって、それに強く惹かれてすぐにコンタクトして、そこで買い付けしたんです。あとは東京に帰ってプランを立て、ビームスの時にやったけれど売れなかったワルター・ヴァン・ベイレンドンクがまたやっているということで、パリの展示会に行って、ワルターのものを今度は僕自身が仕入れる、というようなことをやって、そうこうしているうちに芋づる式に、アントワープのデザイナーに次から次へ会いました。リンダさんが最初にアントワープ展を案内してくれた時に、僕は一人ですごく盛り上がっていたのです、これはすごいみたいなことで。その盛り上がり方がよほど気に入ったらしくて、審査員に来てくれと。なかなかスケジュールの都合がつかなくて、最初審査員はお断りしていたのですが、結局96年に、初めて卒業審査の審査員として行きました。ブリュロートさんがステージングをやっていた時です。それから結局7年間やりました、2002年まで。最後に僕が審査員をやらせて頂いた時は、初めて日本人が三人卒業した時なんですよ。その間にもいろいろなデザイナーと出会いましたね。
マルジェラに関してはすごい人がデビューしたという話だけは聞いていて、西武のシード館でモノだけは見ていましたけど、自分たちも仕入れたいと思ってもルートがなかったのです。が、これまたすごくラッキーなことに1994年にマルタン・マルジェラが全世界の6つの都市の9つの違うお店で同じ洋服を同じ時間にショーで見せるというイベントがあって、その時にある人が日本のユナイテッドアローズで栗野にやらせればということを言ってくださったのです。そのおかげで、いきなり取引することになって、なおかつその日本で初めてのプレゼンテーションをやらせて頂くことになって、僕は当時UAでバイヤーもやりながら、販売促進の部長もやっていたので、プレス兼バイヤー兼オーガナイザーみたいな形で94年にそのプレゼンテーションをやらせて頂いたんです。
西谷:それは具体的にどういうプレゼンテーションだったのですか?
栗野:モデルが12人いて、全世界の9カ所で全員同じ服を着るんです。1994年のマルジェラの秋冬のコレクションの服なのですが。服自体はバービー人形の服を8.5倍の大きさにしたシーズンのものでしたが、モデルについてマルタンから、オーダーがあったのが、我妻マリさん。マリさんはぜひお願いしますと、それ以外はそっちで勝手に探してくれということで、知り合いでマルタン・マルジェラの服が似合いそうな人に、片っ端からお願いして、結果的に、12人の面白いモデルをキャスティングすることができました。日本では時差がありますよね、その他の5カ国とは。実際、やったのは、ニューヨークのバーニーズと、シャリヴァリもやったのかな。それからロンドンのブラウンズとパリはマリア・ルイーザとバス・ストップ、それからミラノのコルソ・コモと、あとドイツのどこかのお店ですかね。ともかく9つのお店の中のひとつがユナイテッドアローズだったのです。で、今のメンズ館の通路を活かしたショーをやりました。当時のマルジェラ社の社長のジェニー・メイレンスさんが下見に来た時は、夏で、ちょうど夏祭りをやっていて、お蕎麦をごちそうしましょうと、神田のやぶそばにお連れしたら、祭囃子が聞こえて来て、ジェニーさんは、その祭囃子がすごく気に入って、これを入れたいと、これをショーに組み込んでくれないかと言うんです。これまた無理難題なのですけど、たまたまこれもラッキーなことに、その年に新卒で面接した女の子が、東京の下町の出身で、和太鼓のチームに入っていたのです。彼女に頼んで、チームで和太鼓やってよということになったのです。今は、彼女は、UAのウィメンズのバイヤーになっていますが。そしてヘアとメイクアップはどうしようという時に、資生堂に行って、平山さんにお願いしたら、メイクアップ全部、無料で提供して頂けたのです。資生堂さんってすごい会社ですね、そういうお金のないショーとか、お金のない若いデザイナーのイベントとかには必ず何か提供してくださって、条件はたった一つなのです、ハンコを押すことなんですよ。資生堂というゴム印がありましてですね、それを押すのです。
平山:入場してきた人の手のひらにハンコを押すのね。これもマルジェラらしいユーモアのあるアイディアですよね。2、3時間は資生堂のハンコが消えないようにと。
栗野:意外と4時間位ぐらい消えないのですよ。忘れて外歩いていると、自分の手を見てぎくっとする。だから、読者としても、『花椿』は中学か高校ぐらいの頃読んでいましたけれども、実際に仕事でヘアとメイクアップをご提携頂くことというのはそれが初めてだったので、平山さんには、本当にお世話になりました。改めてこの場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。
西谷:資生堂はすごい会社だという裏には、平山さんのような方がちゃんといらっしゃるということですよね。
平山:第一回目からマルジェラにはお金がないということがわかっていたわけですから、サポートすることは話し合っていました。現在はディーゼルに入っていますのでなくなりましたが、十数年間は、ハンコを押し続けていました。マルジェラは最初から、匿名性を貫いて絶対に顔を出さない、インタビューは受けない、ということだったのですが、なぜか幸運にも、インタビューをすることができました。それはたぶん資生堂がサポートしていたということがあったのからだと思うのですけども。その時にジェニー・メイレンスさんにもお会いしました。彼女は、マルジェラは非常に才能がある人なのでどうしても後押ししたいと、自分のそれまでやっていたお店を閉じて、二人で会社を始めたのです。そのインタビューの時に、とても印象深かったのは、北の人間は非常に慎み深く、マイノリティなのですと言われたことです。フランダース地方の人は、パリに出て来ても差別があるし、大変つらい思いをしてやってきた。そのアイディンティティを自分たちはきちんと守っていきたいと思っているというようなことを、ジェニーさんも、それからマルジェラ自身も言っていたのです。それで私は、ベルギーの人たちというのはそのように考えるのだということがわかったのです。その後会った人たちも皆そうでしたが、共通しているのは、非常に深くものを考えるということ、それから、やると決めたら必ず徹底してやる、自分の考えを貫いていくという非常に強い意志を持ち合わせている人たちだと思いました。日本人と似ていると言われますが、私たち日本人のほうがもうちょっと弱いのではと、インタビューしたりしながら思いました。マルジェラは、最初の頃は展示会があると全部自分で説明していたんです。一つ一つこれはなぜこのように作られたのかと、自分のコンセプトを非常に丁寧に説明されていたのです、4、5年くらい。だから雑誌には顔が出ないけれども、大方のバイヤーとかジャーナリストは皆、彼の顔を知っていました。その後に会ったアントワープのロイヤル・アカデミーの卒業生の人たちもだいたい同じような説明の仕方をするんです。例えば私はベルンハルトの楽屋に入って取材をしていたことがあるのですが、モデルの一人一人に、この洋服はこういう洋服で、だから、このように着て欲しいし、だからメイクもこうしたいし、歩き方もこのようにやってくださいというのを、丁寧に説明していくんです。ショーの始まる直前で、もう人は待っているのにきちんと説明する暇なんかないでしょうと思うぐらいなのですけれども、それをきちんとやるっていうのは、それもアカデミーで学んだことなのかなと思いました。
西谷:似たような話は、マルジェラの初期のモデルの中に、たまたま昔『装苑』のモデルだった人がいて、その人からも聞きました。帽子が自分の顔に似合わなくて、帽子かぶるのがいやだと言ったらマルタンがやって来て、ちゃんと合うように直してくれたという話で、パーソナルな部分をとても大事にしているんですね。栗野さんに伺いたいのですけども、マルジェラのインスタレーションの後に、例えばヴェロニク・ブランキーノとかA.F.ヴァンドヴォルストを招待なさいましたけど、その辺の中身を知っておきたいのと、それからバイイング的には、さっき高木さんが言っていたように、アントワープ自体よりも日本での方がある意味・・・
栗野:売れていますね。
西谷:どんな風に売れていたのでしょうか。。
栗野:そうですね。一言で言うのはなかなか大変なのですけれども、冒頭のヒェールトさんのお話、それから元学生の方のお話、あるいは今の平山さんのお話でも、共通しているのが、コンセプトということだと思うんですね。おそらく、アントワープの人たちが80年代に、コムデギャルソンやヨウジヤマモトを見て一番衝撃を受けたのは、ファッションはコンセプトであるということだと思うんです。やはり日本の人というのは、今日200人ぐらいですか、皆さん話しを聞きに来てくださっているという事実からも、やっぱりコンセプチュアルなことが好きなんですよね。だから、ファッションを消費財として消費するだけじゃなくて、ファッションに意味を見出すとか、極論を言ったらファッションを生きるということを皆さんしていらっしゃると思うんですね。ファッションに対してただモノとして見つめているのじゃなくて、あるコンセプトが具現化されたプロダクツとして見るということが日本の中に元々あって、特に80年代のコムデギャルソンとかヨウジヤマモト以降は強くあって、その日本人のコンセプト好きというところにアントワープ・ファッションはヒットしたのだと思うのです。それと、どんなに前衛的なことをやってもどこかにクラシックがあるということが、僕はアントワープの強みだと思います。坂部さんたち学生さんはご存知なんですけども、僕が審査員をやらせて頂いている時に一番すごいなと思ったのは、一年生がシーチングとかで割と実験的な服を作っていても、二年生のヒストリカル・コスチュームで歴史を学んで、三年生でエスニック・コスチュームといって要するに民族服を学んで、最終的に四年生で自分のコレクションを作る。つまり、ファッションにとって一番大切なのは、歴史と民族と、オリジナリティですよね。それをちゃんとトレースさせると言うのは、やはり、どんなに新しいことをやっていてもちゃんと歴史であるとか、出自であるとか、それらの背負っているものをいかに大事にしているかということだと思うのです。だから例えばイラン出身の女の子だったら、それはイランらしさ、クロアチア出身の子だったらクロアチアらしさがどこか出ていたし、もっと突き詰めれば、その人個人というものが必ずアントワープ出身のデザイナーの服には出ているのですよ。それを僕なんかは93年のアントワープ・アカデミーの30周年記念プレゼンテーション以降、刷り込まれたので、日本のコンセプト好きの人には絶対これは伝わると思って、紹介し続けてきました。なおかつ面白いのは本人だから、ヴェロニク・ブランキーノにしてもA.F. ヴァンドヴォルストにしろ、やはりその本人を絶対呼ぶべきだなと思って、本人にインタビューをしてもらって、本人とご飯を食べたり本人に浅草を見てもらったり、だからヴェロニク・ブランキーノには歌舞伎を見てもらったり京都に遊びに行ってもらったり、ヴァンドヴォルストとは一緒に東京都現代美術館でマンガ展を見に行ったり、築地で寿司食ったりしましたね。さっきヒューマニティって話しが出ましたけど、やはりそういう中で、彼らのヒューマニティというのが見えて来て、それを何とか商品と一緒にお客さんに届けたいなということを僕はやり続けてきたのかなと。日本のお客さんはそういうのをよくわかってくださるのだと思います。だから今でも、アントワープ・デザイナーの服というのはたぶん、あまりモノとしては見られないのじゃないですかね。ドリース・ヴァン・ノーテンだったら、ドリース・ヴァン・ノーテンの服を通して見えて来る彼の優しさであるとか、自然に対して、草花や木を大事にしていることとか、あるいはアン・ドゥムールメースターだったら、パティ・スミスの詩を大事にしているとか、そういうことをきちんと服の向こう側に見ようとしている、ここにいらしているような方たちがいらっしゃるからこそ、日本ではたぶん世界のどこよりも、アントワープ・ファッションが理解されたのだと思います。例えばアメリカでは、特にアメリカのバイヤーと話していると、「Destroy」という言葉をすごく使うのですね。だからアメリカのファッション・ジャーナリストは、マルタン・マルジェラのことを「King of Destroy」と言うわけです、「破壊の帝王」。でも、彼らは壊しているだけではなくて、壊すことによって作ったわけだよね。さっき平山さんがおっしゃったように、解体と再構築ということをしたわけだから。本当に美しいものを作るために壊すという概念っていうのは、残念ながらアメリカのバイヤーには理解できなかったんじゃないかと思います。あるいは、フランスでも、さっきもお話に出たように、根強い人種差別があって、ベルギー人を馬鹿にするようなジョークって山ほどあるのですけども、そういう感覚からもたぶん、あまり理解されなかったのだろうと。でも、日本は伝統を大事にしつつ、それから、明治維新と第二次世界大戦の敗戦によってやはりカルチャー・レボリューション、カルチャー・ショックみたいなものを経験している国ですから、その中で何かが解体されてまた再構築されていくということを経験し、自然に自分の中に持っているんだと思うのですね。そこにすごくアントワープ・ファッションがはまったのだと思います。
西谷:ところで、アントワープ・ファッションを実際に買う人たちはやはり若い人たちが多かったのでしょうか?と言いますのは、これは私の個人的な考えでもあるのですけど、アントワープの洋服って、最近のドリースなんかは違いますけど、アン・ドゥムールメースターにしても、マルジェラにしても高い割には高そうに見えない。何か洋服にゴージャスなものを求める人にとっては、20万円もかかっているのに、極端にいえば一見H&Mの5千円と変わらないみたいな。実は見えないところですごく手がかかっていたりするのですが、見るからにキラキラ輝いているような服ではないという。逆にそういう一種のポべリズム(Poverism)、清貧な感じというのが、またある種の日本人にはたまらないところがあるのかなと思うのですが、そういう点が若い人たちの賛同を呼んで、お金を節約して、高い20万円のジャケットを買ったりしたのかなと思うのです。たぶんイブニングドレスみたいなものを彼らが作っていたら、こういう受け方はしなかっただろうなと思うのですけど、いかがでしょうか?さっき、平山さんはアントワープに共通する特徴があるとおっしゃいましたけれど。
平山:ベルギーの人たちの静かで抑制のきいた態度などは共通しているけれど、それぞれ違うと思います。ただ、今おっしゃったことで言うと、今は、すべての人にとって、オールマイティに着られる服がある時代じゃないと思うのですね。着る人たちがそれぞれの感情で、私はこの服を着たいという選び方に変わって来ていると思うのですね。ですから、それが安く見えても高く見えても、私はこの服が着たいというその意思の方が、強まっていると思うんです。ですからそこの中には、アメリカのデザイナーもいるし、フランスのデザイナーもいるし、ロンドンのデザイナーもいるし、アントワープのデザイナーもいるというということで、何か洋服の裏側にあるものを、私たちに語りかけてくれるということ、そして、私たちもそこから何かを探し、コミュニケーションをとって服を着たいなという思う気持ちになる。個人的な感情を大切にするきっかけを作ったのがアントワープの人たちじゃないかなと思います。例えば、私はヴェロニク・ブランキーノが好きなのですけれども、彼女が最初に出てきた時は、まだ覚えていますが、グレーのニットの長い、ポンチョが霧の中からふわっとと出て来て、まるで森の中の妖精のような感じだったのですね。その暗いロマンティシズムが、その時は非常に新鮮だったということ。そうなるとそれがトレンドみたいになって来るわけですね。ロマンティシズムとかゴシックというところがですけれども。それは彼女が持っているものが、そうだったと思うのです。その強さがあるから、いろいろトレンドが出て来ても、それに負けない力を持っていると思うのです。
栗野:日本というのは、世界で一番洋服が売れる国だと思うんですね、それはいろいろな意味で。例えば、僕30年来この仕事をしていますけれど、洋服のことを語ったり見たりするのが好きでも、実際に買っている人って、日本が一番多いんですよ。着るし、着て、それを着心地だとか、着た結果その服とコミュニケーションしているというか、だから服に対して理解度も高いのだと思うし、それがヴェロニクが出てきた時の、そういう森の中の少女みたいな部分とか、ベルンハルトが出てきた時のある種諧謔的なポップ性みたいなものを理解してしまう、だから、若いお客さんが多いですけれども、でも、大人の方も買ってくださっているし、どっちかというと、パターン的なことを言うと、アン・ドゥムールメースターの服とか、ドリース・ヴァン・ノーテンの服と言うのは、北方の巨人ですよね、背の高い骨太な女性に似合うように出来ているから、そんなにスキニーな子たちじゃなくても着れるので、そういう意味ではお客さんの年齢層は広いのではないですかね。ただその話題としてそういうものにぱっと飛びつくのはもちろんここにいらっしゃるような方たちが多いと思うのですけど、年齢というよりは、その服に対してさっき平山さんがおっしゃった、その向こう側にあるものを見ようとしたり、向こう側にあるものに共鳴しようとするようなタイプの人が、特にアントワープのものが好きで、例えば例を挙げると、クリス・ヴァン・アッスがディオール・オムのアーティスティックディレクターをエディ・スリマンのあとでやっていますけど、非常に彼はやりづらいだろうと思うのですね。それはエディ・スリマンのあとということで。実際ビジネス的にもとてもしんどいだろうと思うのだけども、でも彼はクリスとしては、もしディオールでなんかやるとしたら、やはりクリス・ヴァン・アッスらしさを出すしかないわけで、だから今クリス・ヴァン・アッスがディオール・オムでやろうとしている、あの過剰な程のロマンティシズムみたいなものというのは、最初はどうするのかなと思ったのですけども、逆に今は肯定的ですね。自分があえてメゾンに雇われたっていうことは、自分にしかできないことをそこでやるべきだ、と彼は思っているのだろうし、そこら辺が良いです。このクリス・ヴァン・アッスらしいロマンティシズムを出していくというのは、すごく納得できますね。で、逆にクリス・ヴァン・アッスが自分で作っているコレクションのシグニチャーライン、クリス・ヴァン・アッス・ネームの服の方はとてもリアルで着やすい服だったりするのですね。でも持っているマーケットの大きさっていうのはディオールの方が大きかったりするので、その辺がアンヴィヴァレントな感じというのが非常に面白いし、彼はそこをどう生き抜いているのかなというのはすごく興味がありますけどね。
西谷:まだ聞きたいことがいっぱいあるのですが、そろそろ時間なので、あとは皆さんから、今までの、一部、二部も含めて、ご質問を受けたいと思います。最後に、私の作っている『ハイファッション』で、いろいろな世界のジャーナリストやバイヤーの方に、今の危機をきっかけに、ファッションがどのように変わるだろうかという、チェンジをテーマにインタビューをしたのですね。そうすると、大方の人の意見は、これから洋服は、大きく二つに分かれるだろうと、一つは高くてもクリエーションがきちんとあるものと、あとはもう安い服とに二極化するのではないかというのですが、やはりアントワープのこの展覧会をきっかけに、クリエーションということについて、もう一度、服の背後にあるものまで見るような、それを買うか買わないかは別として、見るような姿勢をもう一回改めて持って欲しいと思いました。展覧会には映像も沢山あるので、そういうのを見ていくと、きっと何かがあるのではないかと思います。ではありがとうございました。
第二部:アカデミーのカリキュラム
第三部:日本における受容